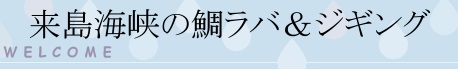
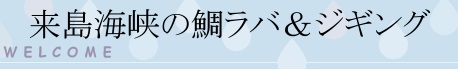
| ��o�i��J�u���j | ��o�̎��� | �W�M���O�A�i�u������ | �^�`�E�I | �^�b�N�� | �A�V�X�g�t�b�N | �_�o���� | ���[���̉��� | �D����̃T�r�L | �u���O | �����N |
|---|

| ���b�h |
�W�M���O�ł�6�t�B�[�g�O��̃��b�h���g���₷���ł��傤�B�^�b�N����3�Z�b�g���炢����ƕ֗��ł��B |
���[�� | ���[����4000�Ԃ��炢����6000�Ԃ��炢�ł������b�h�Ƃ̃o�����X�Ǝ����̑̂ɂ������^�b�N�����g�p���܂��傤�B |
|---|---|
| �W�O |
�W�O��100g���炢����150g�O��܂ł���ł����A�H�Ȃǂ̓^�`�E�I���x�C�g�ɂȂ��Ă��āA���̎���200������250g���炢�̃����O�W�O���g�p�����肵�܂��B |
���C�� |
PE��3���O����g�p���܂��B���[�_�[��40�|���h����50�|���h���g�p���Ă��܂��������ł����܂�H���͕ς��Ȃ��ł��B |
| �t�b�N |
���̓W�M���O�ł̓g���v���t�b�N�͂قƂ�ǎg���܂���B�g�p���鎞�̓T�������܂���Ƃ���^�`�E�I�A�^�ⓙ��_���������ł��B |
| �A�N�V���� |
�W�O�̓��������͂��̎��̏ɂ���č��ꍏ�ƕω����Ă���̂ł��ꂪ�����Ƃ����̂͂���܂��A���̎��̂�����p�^�[���𑁂������邱�Ƃł��B |
| �����f�B���O |
�����f�B���O�͌o�����Ȃ��Ƃ킩��Ȃ����Ƃ������ł������S�҂̐l�̓|���s���O�����悤���^���ł���Ă��܂������\�e���V�����������Ă���l�������̂Ń��b�h�����낷����������ƃ��[���̓����ɍ��킹�ă��b�h���d�����̂��ێ����Ȃ���s���Ă��������B |
| �W�M���O�ɂ��čl���� | �W�M���O���S�҂̕��݂͂Ȃ���悭�W�O�����܂��B |
|---|
| �d�|���ő啨�Ƀ��C���u���C�N����Ȃ������ |
�����C���ł͑���PE���C���͎g���܂���B���ꂪ�����ꂪ�Ƃ�Ȃ�����ł��B |
|---|
| �i�u���ɂ��� |
|---|
| �܂��̓i�u���ɂ��Ēm���Ă����܂��傤�B �i�u���Ƃ͐��ʂ܂Ńn�}�`���̋����x�C�g��ǂ������ăo�V���o�V���ƌ����܂��B �i�u���ɂ͑傫�������ĂQ��ނ���܂��B ��́A������n�}�`�Ƃ����Ǐ�����߂炦��̂͊ȒP�Ȏ��ł͂Ȃ��̂ł��B�L���C�̒��A��Q���◬��̖������ł͂ǂ��ɒǂ��l�߂邩�H����͊C�ʂł��B �����͂���ȏ�A��ɂ͓�����܂���A�ߐH���͌Q�ň͂�ŕߐH���܂��B ���ׁ̈A�傫�ȉ~�̂悤�Ȍ`�Ńi�u�����N���܂��B �����Ă�����̃i�u���͗���̋������⒪�ځA�����Ă����オ��ɂł�i�u���ł��B����͎��͂ނƂ������͕ߐH�����������ʂ������Ƃ��������ł��B ���������ꏊ�͏��������ꂪ�����j���Ȃ��Ȃ�������ߐH���Ă���̂ł��B���̃i�u���͐�����C��ł��n�}�`���ߐH���Ă���ꍇ�������ł��B �����i�u�������̓���Ȃ��W�M���O����̂ł������҂̃i�u������Ȃ��ƒނ�܂���B �T�r�L�������ł��B ���߂͂킩��Ȃ������m��܂��A�����ȃi�u�������Ă���ԂɈႢ���킩��ł��傤�B �����C���̌����̒��ł̓i�u���ɂ͂Ȃ�ɂ����̂ł����A����͐��ʉ��ŕߐH�ł��邩��ł��B���ꂪ����̂Œ��ڂ��Q���A�����オ��ɓ��钪�ŕߐH���Ă��܂��B �Ƃ��낪�����キ�Ȃ����Ƃ��͈͂ޑO�҂̃i�u�����ł܂��B ���̂��Ƃ�����ꏊ�ł͂Ȃ����̓����ɂ���ăi�u���̎�ނ��Ⴄ���Ƃ��킩��ł��傤�B �����オ�蓙�̒n�`�ɂ��܂�ω����Ȃ����� �͂ރi�u�����o�Ă��鎞��U���ōL�͈͂ɏo�Ă��鎞�ɃW�M���O��T�r�L�ő_���̂������ł����A���Ɍ����������ł��B �͂ރi�u���̎��͉��ł͌����g�킸�ǂ��l�߂邾���̎�������܂��B �傫�ȃx�C�g�̌Q���ǂ��l�߂Ă��鎞�ɃW�O��H�����Ƃ����̂͋^��ł��B ����������ɒǂ��l�߂�Ή��\�C�Ƃ���������x�ɐH�ׂ�鎖�����͒m���Ă�ł��傤�B �U���̃i�u���̕����W�O�ł͐H���Ղ��ł����A�ǂ��Œǂ��Ă邩���킩��܂���B ��������オ��⒪�ړ��̃|�C���g�����������_�������̂ł����A���������̂��Ȃ����ł͌����������ł��B �����������ł��i�u�����������ő_���̂Ȃ�W�M���O�͓_�ő_���悤�Ȃ��̂ł��B �W�M���O�D�ő吨�ŃW�O�����̂Ȃ�܂������ł��B �W�O���x�C�g�̌Q��Ɍ����ė��ꂽ���ŃG�T��T���Ă���n�}�`�ł��A�x�C�g�̌Q�ꂾ�ƃA�^�b�N���Ă��₷���ł��B �������n�}�`���Q�ꂾ��1�C�|�����đ���Ƒ��̃n�}�`����C�ɐH���������܂��B ���ׁ̈A�W�M���O�D�͈�x�ɉ��C���ނ��̂ł����A���͊�{�A��l�Œނ�܂��B �����������͏o���Ȃ����߁A���͂悭�i�u������1�{�Œ��ނ̂ł��B �W�M���O�͐��[�̂��鏊�Ȃ�^�i�Əꏊ���s���|�C���g�ł��ĂȂ���Ȃ�܂���B ���ʁA�W�M���O�|�C���g�͋��Ă�̂ł͂Ȃ��n�`�̕ω��̂���Ƃ���ŁA�G�T��T���ɗ����������Ă܂��B �T�o�͌Q��������ė��Ƃ���������܂����E�E�E �n�`�ω��̂Ȃ����ŋ���T���̂Ȃ�\�i�[�ł��Ȃ��Ƃ����Ɍ������܂��B �K���ɃW�M���O���Ēނ�Ă��A���̒��ł́u�ނꂽ�v�����Łu�ނ����v�ł͂Ȃ��ł��ˁB �����x���S�R�Ⴂ�܂��B ���̓_�A�i�u�������Ȃ�ߐH���Ă��鏊��_���܂��B ���[�̐��Ȃ�i�u�����o�Ă��Ȃ��Ă��p�ɂɃi�u�����o�Ă���|�C���g�͐��ʂ��ӎ����Ă��鋛������ł��傤�B �����u���O�ʼn��x�����ނ��Ă���̂͂����������R�ł��ˁB �����L���X�g�Z�p�A���A�[�̑I���A���������͔��ɃV�r�A�ł��B �W�M���O�͐��[�����邽�ߐ����͈Â����炩���ƃA�o�E�g�ł��B �������i�u�������͌������Q�ɓ����Ă���\�w�ł��B �|�b�p�[���̐��ʏ���������A�[�ȊO�͊��S�Ɍ��ĐH���Ă��܂��B ���x���ǂ��Ă��邪������ꍇ�͐F�A�T�C�Y�A�����̂ǂꂩ���Ⴂ�܂��B�i�������F�̓A�s�[�����ǂ��ꍇ�ƃi�`���������ǂ��ꍇ������܂��j ������ł��H���Ă��鋛���Q��̒��ɂ͂���̂ŁA1�C�ނꂽ�̂�����E�E�E�Ɖ��x���i�u���ɒʂ��Ă��܂������ł����A�{�����}�b�`�U�x�C�g�Ȃ�p�ɂɃA�^�b�N���Ă��܂��B �ǂ����t���i�u���̉��ɂ͂����Ƃ�������̃n�}�`������ƌ����܂����A����͌�҂̃i�u���ł̘b�ł��B���̃i�u���͋��t���g���T�r�L�ł��ނ�܂��B ���̌��ɂ߂��ł���A�Ⴆ�W�O�Ńi�u�����������Ă��鎞�ɂǂ̑w��_�������킩��܂��B �O�҂Ȃ琅�ʒ����␅�ʏ�˂����Ă���ƌ��ʓI�ŁA��҂Ȃ牺�ɒ��߂Ēނ邱�Ƃ��o���܂��B ���̏ꍇ���̕����H�����������Ƃ������ł��ˁB �܂��x�C�g�ƃ��A�[�̑傫���⓮���������炩�ɈႤ���́A���ʂ˂����ƌ����ĂȂ��̂ŐH����������̂ŁA���x���i�u���ɒʂ��Ă��H��Ȃ��Ƃ��͎����Ă��������B |
| �i�u���߂Ȃ��ׂ̒��� |
| �͂ރi�u���̒��߂Ȃ��ׂɋC�����邱�Ƃł��B ���ڂɂł�i�u���͌x���S�����Ȃ����X�̎��ł͒��݂܂���B�C�ɂ����K���K���ނ�܂��傤�B ��ԑ厖�Ȃ͉̂��ł��B �x���S�������Ƃ��͑D���߂Â��������Œ��݂܂��B�D�̔g�艹�Ń_���Ȏ�������܂��B ���̂Ƃ��͂��Ȃ藣�ꂽ�ʒu���牓�����đ_���܂��傤�B ���R�A�f�B�[�[���D�̉������݂₷���ł��B �����đ�����C�P�}�̊J���߂̉��A���������C�̎��R�E�ɖ������̓_���ł��B ����ނ��ċ����o�^�o�^�Ɩ\��鉹���x�����܂��B�o���邾���C��t���܂��傤�B ���E�I�Ȏ��ł�PE���C���̋}���ȓ����ɒ��ӂ��܂��B�L���X�e�B���O�����炢�̓����ł͑��v�Ȏ��������ł����A���[�����O���Ă��ċ����|����������PE���C�����傫�������悤�Ƀt�b�L���O����ƁA��C�ɒ��݂܂��B �����Ŏ��͊��������̊����ŏ��������b�h����O�Ɉ����悤�Ȋ����Ńt�b�L���O���A���S�������ŋ����������Ȃ��悤�ɌQ�ꂩ����������܂��B �L�т̖���PE���C���ƁA������Ƃ����j��Ȃ���v�ł��B ���b�h�̓��A�[�ƈ꒼���ɂ��܂��B���̕��@�ɂ��t�b�L���O���ɑ��̋���PE���C�����G��Ẵ��C���u���C�N�������ɖh���ł���܂��B �����^�i�ŋ������������Ă���Ȃ�i�u���̒���ʂ낤���i�u���͒��݂܂���B �i�u���̒��Ń��[���������̂��~�߃��b�h�ł��߂��肷��Ƌ�������̂Ń_���ł��B �ӊO�ƃt�b�L���O���Ȃ��Ŋ����Ă���ƒނ�ꂽ���ɋC�t���Ȃ��̂���r�I���ƂȂ�������Ă��܂��B �i�u�����痣���ƃK�b�c���ƃt�b�L���O���Ă���肵�܂��B �����H�����u�ԂɃt�b�L���O���Ă��܂��Ɗ|�����������������Ē�R���܂��B���̎��ɉ��ɐ�������X���Ɠ����悤�ɂȂ�܂��B �X���Ŋ|���Ă��܂��Ɗ|�������������Ă��܂��A����ɘA����Ă��܂��̂ő��̋�����C�ɒ��݂܂��B �����Ȃ��Ă��܂��ƐH�����������͌x���S�������A������H���������Ȃ鎖������܂��B �X���Ŋ|�������Ȃ��H�킷�Z�p���K�v�ł��ˁB�݂�ȂŌ����Ă���Ƃ��Ɏ������|�����u�ԂɃi�u�����u�o�V���b�v�ƈ�C�ɒ��ނƎ����̂����ő��̐l���ނ�Ȃ��Ȃ�܂���B �i�u���̒����W�n�тő������ň����|����悤�Ɋ����悤�Ȗ��_�o���ł͒ނ�Ă��P�C�ł��B��������Ζ��Ȃ��ł����B�������X���̓o���₷���ł��B �D���~�߂�ʒu���厖�ł��B �ߕt���Ȃ���i�u���̐i�ޕ���(�i�u���͌��\�o�Ȃ���ړ����܂��j���A���v�Z�ɓ���đD���~�߂܂��B ���̎��ɂ܂Ƃ܂����i�u���Ȃ�K���i�u���ƑD�̊Ԃɂ���肷��X�y�[�X���m�ۂ��Ă����܂��B �i�u�����狭���Ɉ�������o�����n�}�`���A��������K�b�c���ƃt�b�L���O���Ă���肵�܂��B ���̎��ɋ����傫���������x������ł��傤�B �ł��i�u���Ɨ���Ă���̂Ńi�u�������ނ��Ƃ͂���܂���B ���ꂪ�i�u���̂������Ő�����ƃi�u�����u�o�V���o�V���v�ƈ�C�ɒ��݂܂��B ��������������A��C�ɏグ�Ă����Ȃ���Ȃ��ł����B |
| 1�b�ł������i�u�������邽�߂� |
| �i�u�������ő厖�Ȏ��͑����i�u���ɃL���X�e�B���O���鎖�ł��B ���ׂ̈ɂ͑��������鎖���厖�ł��B �i�u�����ł����Ȋ����̓Ɠ��̐��ʂ������鎖�Ⓓ�̋߂��őҋ@���Ă��铙�ł��B ��ł͖����ł������̓������d�v�ł��B �z��͐��ʉ��ł̋��̓����������Ă���̂ŁA�ǂ̕����ɏ�����ǂ��l�߂Ă邩���킩��܂��B ���Ǝv���̂�т�x��ł��鏊�̂������Ƀi�u�����N���Ă���̂ɋC�t���̂��x�������������肷��̂ŁA�������𗊂�ɂ���̂������܂����B �g�����Ȃ��Â��Ȏ��͎��E�ɗ���������o�ɗ��� ���������Ƃ�������܂��B �Ȃ�Ă�������360�x���ׂĂ��������܂�����B�����������͎��E�͉����A���o�͋߂��ɏW������Ɨǂ������o���܂��B �ł������i�u���͎��E�Ŋm�F�ł��Ȃ������ł��A�������͕������Ă��鎞������܂��B �����������̃i�u���̑傫���̓n���p����Ȃ��ł���B |
| �P�C�ł������i�u�������ŕ߂邽�߂� | �ނꂽ���͏o���邾�����Ƃ�𑁂��s���܂��B �i�u�������߂������������y���߂����ł����A�i�u�����p�����Ă��鎞�̓S���������܂��傤�B �����ă����f�B���O�̓t�b�N�����܂Ȃ��l�b�g���g�p���邩�����グ�܂��傤�B �Ԃ̃l�b�g�̓g���v���t�b�N������Ŏ��������ɓ�����܂���B ���������グ�͐g���b�h�j���A���̐l�Ɋ댯������܂��̂ŋC��t���܂��傤�B �����Ƀt�b�N���O����悤�Ɏ�܂����Ă��܂��B����͎w��̕ی������܂����A�Ȃɂ�苛��h�݂͂ɏo���邩��t�b�N���O���₷���B ���̂������M���b�Ɖ�������Ƌ��͂��ƂȂ����Ȃ�܂��B ���ꂩ��t�b�N���O���܂��B �S���������ďオ���Ă������̗͑͂��L��]���Ă��邽�ߑD�ɏオ���Ă�����ɖ\��܂��B ���̏�ԂŃt�b�N���O�����Ƃ���Ɖ���̋��ꂪ����̂ŁA�����Ȃ��悤�ɌŒ肵�ăy���`���ŊO���܂��傤�B �e���|�ǂ��o����i�u�������Ȃ�Q���މʂ�����������܂���B�m���ɐH���C������A���������Ă���̂ł�����x�C�g�ƃ��A�[�������Ă���Δ��ށA�ԈႢ�����ł��B |
| �i�u���ƒ��̊W |
�悭�̂��璪�~�܂�͋����ނ�Ȃ��A�Ƃ����̂�����ł��ˁB �����ǃn�}�`�i�����T�j�̃i�u�������Ɋւ��Ă͂����Ƃ�����܂���B ���~�܂�O����Ԃ��̒��������܂Ńi�u�����o���ςȂ��Ƃ������Ƃ�����܂�����ˁB �Ȃ����~�܂�͐H��Ȃ��̂��E�E�E ���R�͑��� �@�T�r�L���Ȃт��Ȃ� �A�H���C������ �B�G�T���߂�ɂ��� ������Ȃ����Ǝv���܂��B �@�̓i�u���ɂ͊W���Ȃ��̂ł����A�̐H���C�������́A�Ẵn�}�`�ɂ͐H���C�������͖̂邾������Ȃ����Ǝv���܂��ˁB �݂̒����p���p���œ������������Ă邾�낤�Ƃ������炢�H���Ă�z�ł��i�u�������ł̓K���K���H���Ă��܂��B �������b�ł͉Ẵn�}�`�̏��������͂������炵���ł��B ������`�����X����ΐH��������ł��傤�ˁB �B�̃G�T���߂�ɂ����͒��~�܂�̐����ł̓x�C�g�͎��R���݂ɓ����鎖���o���܂��B ���ׁ̈A�n�}�`�����ʂɒǂ��|�����Ƃ��������ߒǂ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �W�M���O�A�G�T���ɒ��~�܂�́A�قڒނ�܂���B �������������낦�G�T���ߐH�ł���ׁA�i�u���Ȃ�H���܂��B ���̏����Ƃ́A�n�}�`�ƃx�C�g���ɑ傫�ȌQ��̏ꍇ�ł��B ���ׁ̈A���~�܂�ɏo������i�u���͌��܂��ăn�}�`���x�C�g���͂�ł܂����ɂȂ�i�u�����ł܂��B ����Ȃ璪�~�܂�̗���̂Ȃ����ł��ȒP�ɕߐH�ł���̂ł��B �������P���ŏo��̂�����܂����ނ�ƂȂ�ƁA�ǂ��ɏo�邩�����������Ȃ���ɂ����ɒ��ނ��Ƃ������̂œ���ł��B ���������~�܂�O��͑�i�u���̃`�����X��������܂���B �ǂ����₳���̂��u�ǂ̒����i�u�������ɗǂ��̂ł����H�v�ƕ�����鎖�������ł����A�ǂ̒��ł��������o�܂��B �����咪�̓i�u���̎���������Ə��Ȃ���������܂��B �����n�߂̗ǂ����Ńi�u�����o�Ă��Ă��A�����ɗ��ꂪ�����Ȃ�o�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����܂����A����̎ア�|�C���g�Ȃǂ͋t�ɗǂ������肷��̂ň�T�ɂ͌����܂���B ���ꂼ��̒��ŗǂ��i�u���̏o��ꏊ������܂��̂ł��̒��̎��ɁA���̃|�C���g�ŏo���A�Ɗo���Ă����܂��傤�B �������x�C�g�A�n�}�`�Ƌ��ɌQ�ꂪ���������ɂ����o�Ȃ��̂Ő�ł͂Ȃ��ł��� �i�u�������x���o��|�C���g�̓i�u���ɂȂ�₷���D�������m���ɂ���܂��B �����p�ɂɃi�u�����ł���̂́A�悭�o��|�C���g�����ɓ����Ă��邩��ł��ˁB �i�u����������͂��K�v�ł����B |
�������p���Ă��郉�C���V�X�e����SF�m�b�g���ł��B
YOUTUBE�̓�������Ă��炦��킩��܂����A���͂P���҂ݍ��݂͂��܂���B
���R�͒P���ɖʓ|�������A���Ԃ�������B�u�h���D�̏�ł���Ȏ��ł��邩�I�v�Ǝ����ōl�����̂������݂��܂����B
����Ă���ƕ҂ݍ��悤���Y��Ɏd�グ�邱�Ƃ��o���܂���B
�n�߂ɂQ�O��ȏ�PE���C�������[�_�[�Ɋ������܂��B���������ƉE���߂��E�����Ɉ�������n�߂Ɋ�������PE���C���̏�Ɋ����Ԃ��܂��B
�����ĂW�̎����тŎ~�߂܂��B���̎��̒��ӓ_�͑��ł������ł����A��p�̃V���R���ł��\���܂��A�悭����悤�ɂ��Ă����܂��傤�BPE���C���͔M�Ɏア�ł��̂ŁB
����ƃ��[�_�[�i�W�O���j�������āAPE���C���̃��[�����A�]���PE���C���A���[�_�[�̗]��A���ׂĂ���������A�\���ɒ��ߍ��ގ�����ł��B
���ʂ�SF�m�b�g�͕҂ݍ��݂����ĂW�̎��A�������̓��j�m�b�g�ŏI���ł��B
���ꂾ���ł͋��x�A�ϋv���s���Ȃ̂Ńn�[�t�q�b�`���P�O��قǍs���܂��B
���ꂾ���ł����x�͏オ��܂��B
�����ă��[�_�[��]�����ؒf���ă��C�^�[���t���ăR�u������Ă����܂��B
���������Ă����Ȃ��ƃL���X�e�B���O�Ȃǂʼn��x���K�C�h��ʂ邤���ɃX�b�|�����邱�Ƃ����邩������܂���B
�Ō�ɂ�����xPE���C�����n�[�t�q�b�`��PE���C���̏�ɂP�O����s���܂��B
����̓��[�_�[�̍Ō�̕�����PE���C���̌ł����Ⴂ������ׂɋ��ڂ�PE���C���ɕ��S���|���肷����̂ŁA������y��������ړI�ł��B
������PE���C����ؒf���ă��C�^�[���t���Ċ����ł��B
�n�[�t�q�b�`�͍��E���݂ɂ���l�����܂����A���x��ϋv���͕ς��Ȃ��̂ŁA�X�s�[�f�B�[�ɂł��铯�������ł���Ă��܂��B
�W�M���O�A�L���X�e�B���O�A�G�M���O�A���ׂĂ���ōs���Ă��܂��B
�W�̎����т̃R�u�������Ƃ����l�͂��̕��@��FG�m�b�g�������߂��܂��B
�����ȑO�̓L���X�e�B���O��FG�m�b�g���g�p���Ă܂������ASF�m�b�g�ł��A������ƌ��іڂ��Q.�R�K�C�h������Ɏ����Ă���悤�ɂ��Ă���A�L���X�e�B���O���Ɍ��іڂ������|�����Đ�鎖�͂Ȃ��ł��B